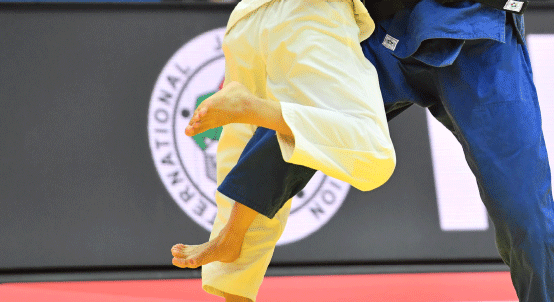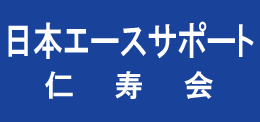――44年にわたる指導者生活のなかで、ターニングポイントとなった出来事や忘れられない出会いがありましたら教えていただけますか。
忘れられない出会いということで一人挙げるとすると、52kg級のイザベル・シュミットという女子選手です。すごくまじめな子でした。私が30歳頃のことです。毎日練習しましたし、毎週末、試合に行ったり、私がよその国で指導をするときも連れていって練習をさせました。何度も国内チャンピオンになりましたし、国際大会でも結果を残しました。私が何を言ってもついてくるし、何でもやる。そうするとどんどん教えたい気持ちが湧いてくる。すごくうまくいった選手でしたね。
でも、そういう生徒と巡り会うと、そのあと教える気がなくなってしまいますね(笑)。同じようにやっても、不真面目な子はついてきてくれない(笑)。私も、それだったらいいやってなってしまったときがありましたね。でも、そこからだんだんと柔道が好きな人に教えたい、ついてきてくれる人に柔道を教えたいという気持ちになっていきました。

――ナショナルチームに携わられた時期もあったとうかがっています。
1979年に女子のナショナルチームのトレーナーになりました。ニューヨークで初めて女子の世界選手権が開催される前の年です。トレーナーというのは稽古をつける人のことですが、これをやってみてわかったのが、基本練習ができていない選手が非常に多いということでした。受身、体捌き、練習姿勢、すべてです。
それでこちらでは基本練習が足りていないということがわかりましてね。自分のクラブやセミナーでは、基本を教えていかなければならないと気づいたわけです。だから、やりがいがありました。私は基本から始めるのが好きでしたから。それに柔道をやってよかったなという気持ちになってほしいと思っていましたから。

――柔道をやってよかったなという気持ち。どうしたらそういう気持ちになってもらえると考えていましたか。
教え子に2008年の北京オリンピックの81kg級で3位になった子がいるんですけど、ある日、その子がウエイトルームから裸のままで道場に入ってきました。道場に裸で入ってくるなんて、礼儀がなっていない。だから、叱るわけです。「君はオリンピックでメダルを獲ったかもしれないけれど、子どもたちの見本にはなれていない、大人になるべきだ」とね。
つまり、柔道を通じて、自分自身をわきまえる力を身につけていってほしいと考えてきたんです。人と助け合い、人に必要とされるような人間、嘉納治五郎先生の言う人の役に立つ人間になるということでしょうね。強くなるのはいいことだけれど、道徳心を持って、大人として社会で生きていくことができるようになること、それを柔道から学んだと思ってもらえればいいと思ってやってきましたし、今も思っています。