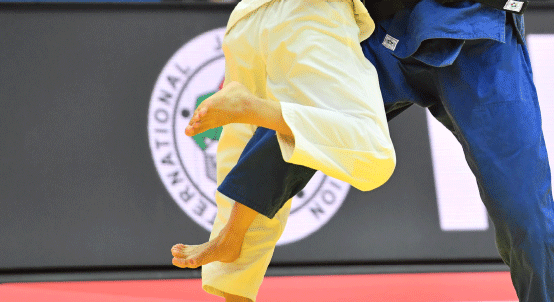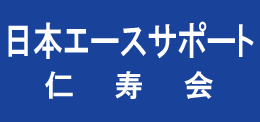青年海外協力隊(JICA)柔道隊員としてバングラデシュに赴任したことを皮切りに、ミャンマー、中国、そしてカザフスタンで指導されてきた千原慎太朗さん。自身の選手としての実力に限界を感じた大学時代、次のステップとして目指したのが海外における指導者でした。今まで指導を行ってきた4か国については、文化や生活習慣が大きく異なる国々でした。しかし、柔道指導という観点では現地の選手や指導者と信頼を築くことから始めるなど共通する点は多くあり、選手が人間性をも身につけられるような指導を心掛けている、と語ります。第10回は、現在、カザフスタンで柔道指導をされている千原さんにお話を伺いました。

――海外に出られたきっかけを教えてください。
大学の海外武道実習でフランスに行かせていただいて、子どもたちに柔道を教えているときに、言葉ができないなかでも通じ合えて、ビビっと来るものがありました。柔道でコミュニケーションが取れるという感覚、自分を必要としてもらえる場所だという直感、そして自分のいる柔道というジャンルは日本人であること自体に価値を感じてもらえるものだなと。また、選手としてはもうあまり見込みがないとわかっていたのですが、できればもう少し柔道に携わっていたかった。で、進路を決めねばならない4年生になったときに、JICAが行っている青年海外協力隊の存在を知ったんです。当時、大学に形の授業の講師としていらしていた佐藤正先生に相談してみたところ「行け!」とその場で講道館に電話してくださって(笑)。トントン拍子に話が進みました。

――その後、現在のカザフスタンに至るまで4か国で指導。それぞれまったく違う文化のなかで異なるミッションを担ったわけですが、最初の任地であるバングラデシュでの指導はいかがでしたか?
ナショナルチームといっても1つの体育館でいくつもの競技が練習をしていて、練習場所は事前に柔道に割り振りされた時間しか確保できませんでした。選手全員が揃うことはまずない。現実を見て、まずはできることをしっかりやろうと考えました。選手が毎日厳しい練習をすること自体に慣れていないので、メニューを工夫して目先を変えながら、柔道にこだわらず「毎日やる」という習慣をつけることから始めました。この国のキーワードは宗教、イスラム教ですね。女子の試合では、「礼」をするなり棄権する選手もいて、1試合もせずに優勝者が決まることもありました。練習中もお祈りがあると中断です。もちろんその行為は尊重しますが、なかには練習がきつくなると「ちょっとお祈りしてくる」と言っていなくなって、喫茶店でお茶していたり、隠れて寝ている選手もいました。でもこれはうまく理解していくと良い面もあって、「勝敗はアッラーが決めるものだ」と試合が近づいた選手が言うと、「アッラーは、試合に出るたくさんの選手のなかで誰を優勝させると思う? 一番努力した人だと思うよ」と諭すと「ああ!そうか!」と納得してくれたり。JICAの研修でベンガル語を学んでいたことも非常に助けとなり、海外での指導にはその土地の言葉と宗教、生活習慣を理解して尊重することが大事だなと肌身で学んだ2年間でした。