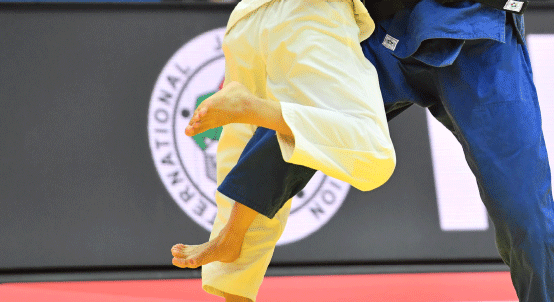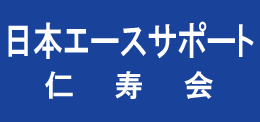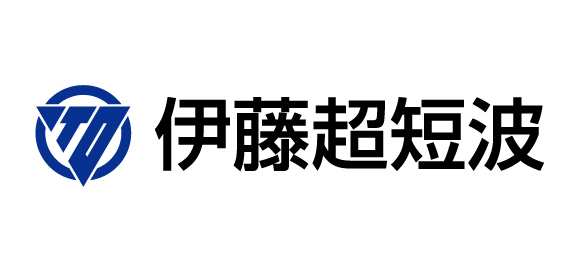プロフィール
廣川 充志(ひろかわ みつし)1977年 富山県生まれ
桐蔭横浜大学 准教授 柔道部男女総監督
講道館柔道六段
主な活動歴
2004年~2011年 柔道ルネッサンス委員会委員
2010年~2017年 国際委員会委員
2012年~2021年 強化委員会委員
2017年~2023年 女子柔道振興委員会副委員長
リオデジャネイロ五輪男子コーチ(90kg担当)
国民体育大会 神奈川県女子監督
桐蔭横浜大学の廣川と申します。2017年に全柔連女子柔道振興委員会副委員長の役職を仰せつかり、はや7年弱の年月が経過しました。委員の任期が終わりになることもあり、僭越ながら委員という立場でJJVoiceを発信させていただきます。
委員就任当初、正直女子柔道のことを何も知らない私で務まるのかと思いながら会議に参加していたことをよく覚えています。参加メンバーのほとんどが女性で構成される本委員会。毎回極度の緊張で委員会に臨んでいました。その感覚は結局最後まで変わることはありませんでしたが、委員の皆さんがとにかく明るく、その快活さに毎回助けられたと感じます。今日までの間委員を継続することができたのは、間違いなく松田基子委員長、中村淳子副委員長、南條和恵副委員長、そして各女性委員の皆さまのお陰であったと思います。
委員会は常に活発に議論が行われていたと感じます。実現可能かは問わず、何よりも委員の皆さんが常に前向に発言されていたことが非常に印象的でした。その中で、大学生をターゲットに実施した「女子柔道キャリアアップセミナー」、全都道府県から代表者を集め実施した「女子柔道意見交換会」、女性柔道経験者の掘り起こしを狙った「COMEBACK女子柔道プロジェクト」、全柔連webサイト内、「女子柔道専用ページ」の開設と「JJVoice」(←こちらはHPを見てもらうためにスタートした企画となります)、さらには、育児と柔道の両立を支援する「スマイルルーム」の推進など、委員会として数多くの事業を実施できたことは本委員会の誇るべき成果といえます。
私はこれらの取り組みを通し、女子柔道のエネルギーが高まれば良いなと考えていました。最初は小さな活動でも続けることで大きくなり、それがいつかは大きなうねりとなって社会全体に影響を及ぼす。世の中の変革は常にそのようにして起きることを考えると、松田委員長の下、女子柔道のムーブメントを起こす最低限の下地は造れたのではないかと感じます。そして7年間の委員会を振り返り、次に示す3つのことを強く感じましたのでこの場を借りてお伝えしたいと思います。
①女子柔道は人材の宝庫である
立場上、キャリアアップセミナーや意見交換会で様々な女性とお会いする機会に恵まれました。その中で率直に感じたことは、素晴らしい女性が沢山いるということです。私が言うのも大変おこがましいですが、能力に長けた素敵な女性が柔道界には沢山存在します。大切なのは、それらをどう掘り起こし、どう繋がっていくかということです。勿論、社会全体の構造的な問題もあります。ただ、閉塞しきったこの柔道界を変えていけるのは、間違いなく女性のパワーだといえます。そして、その人材はきっと皆さんの身近にもいるはずです。
経済の世界でしばしば使われる「平成の失われた30年」。この背景の一つに、女性の社会進出が世界と比較して大幅に遅れたことが挙げられています。柔道界も例に漏れずでしょう。先に述べた人材の掘り起こしと連携、このシステムが構築されれば、柔道界の未来はとても明るいと感じます。その為には、ある一定のアファーマティブアクション※も個人的には必要であると考えます。
②女子柔道の問題は男性の問題である
なぜ組織に女性役員が少ないのか、なぜ女性指導者が少ないのか、なぜ競技引退後に女性は柔道から離れるのか。それらの問題のほとんどは男性側の問題であり、男性が本気になって考え、改善を試みることでその多くは解決できると考えます。つまり、優秀な女性柔道家たちを眠らせているのは誰なのかということです。このような話をすると、必ず女性の資質や能力に疑義を示す人が出てきます(前述の通り実際には優秀な女性柔道関係者は沢山います)。もし仮にそうだとしても、それを周囲がサポートすれば良いだけの話です。私自身は男ですが、性別を問わず多くの方に支えられてきました。だからこそ、今でもこうして柔道に携わる仕事が続けられているのだと思っています。
委員就任後からこのこと(女性に関する問題は男性の問題であるということ)は強く感じていました。私は多くの男性指導者と意見交換し、その都度「男性が女子柔道の未来を本気になって考えなければ絶対に変わらない」と訴えてきました。それが委員会で副委員長を務める男性としての私の役目だと感じたからです。この考えは今も全く変わりませんし、今後も言い続けたいと思います。それにより、この視点が持てる男性指導者が増えることを期待しています。
③女性柔道家は「勇者」であれ
私が尊敬する将棋の羽生善治さんの座右の銘に、「運命は勇者に微笑む」という言葉があります。将棋の駒は、(駒の種類にも依りますが)前に進むことも後ろに下がることもできます。迷った時こそ前に進む決断をして、自ら運命を切り開くことを選択すべきという考え方です。現在私は女子大学生を指導していますが、自分の力量を低く見積もる学生も少なくありません。謙遜という言葉で片づけてしまうにはあまりにも勿体ないと感じます。「私には無理です」「私にはこの位がちょうど良いです」という女性自身の気持ちこそが、実は女性の活躍を阻む要因となっているのではないでしょうか。次世代を担う若い女性柔道家の皆さんには、あらゆる機会に積極的にチャレンジしてもらいたいと思います。その勇気ある一歩が他の誰かの一歩に繋がり、最終的に女性が当たり前に活躍する未来へ繋がるのではないかと考えます。
最後に、本委員会が2017年4月に発足した時の、松田委員長が会議冒頭述べられた言葉を紹介して終わりにしたいと思います。
「この委員会は、女子柔道がどれだけ不遇の時代を送ってきたかについて議論しない。それよりも、女子柔道がこの先どうすれば良くなるのか、私たちが今いるこの委員会は常に未来志向で在りたい」
女子柔道の諸先輩方の相当なご苦労を、この一言だけで十分すぎるくらい感じることができました。そして、そのことに無知であった自分をとても恥ずかしく思いました。無知が問題を生じさせるからです。
そこからは、私なりに女子柔道の現状について知ろうと心掛けました。ぜひこのコラムを読む皆さま(特に男性)、少しだけ視野を広げて女子柔道を見てください。そして、女子柔道を取り巻く環境、そこから見えてくる普及や振興の方法を考えてください。その一つ一つが、これから先の女子柔道ひいては日本の柔道を良くしていくと私は確信しています。
※アファーマティブアクション(Affirmative Action):性別や人種等の理由で受ける不当な格差を是正する取り組みのこと。特に女性に対する積極的改善措置のことを、「ポジティブ・アクション (Positive Action)」とも呼び、2019年にスポーツ庁が策定した「スポーツ競技団体ガバナンスコード」で示された女性理事の割合を40%以上の目標も、そのうちの一つとされる。