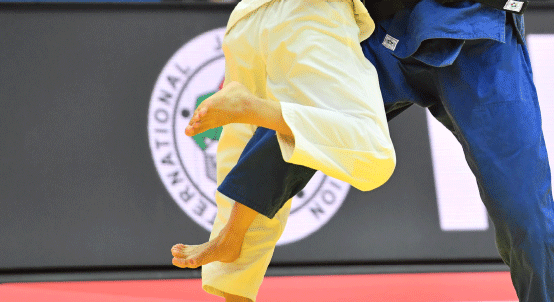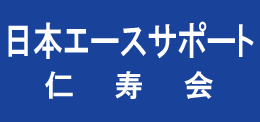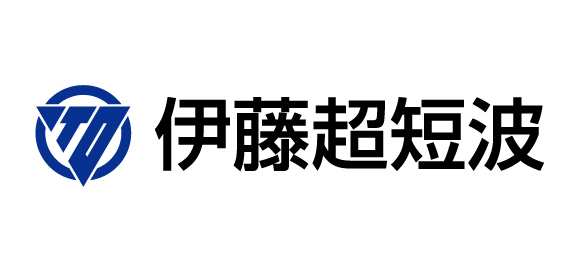プロフィール
南條 充寿(なんじょう みつとし)1972年 愛媛県生まれ
仙台大学 現代武道学科教授(副学長)、柔道部部長
講道館柔道七段
主な戦績
1994年 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会65㎏級 優勝
主な活動歴
2005年~2016年 日本オリンピック委員会強化スタッフ(コーチングスタッフ)
2013年~2016年 全日本柔道連盟強化委員会・女子監督
2018年~現在 全日本学生柔道連盟理事
【はじめに】
今回、女子柔道振興委員会からの推薦を受け、この企画に登場させていただきました。
まず、130回の継続を維持しているこの企画やCOMEBACK女子柔道、キャリアアップセミナー等のイベントを実施し、女子柔道の普及発展のためにご尽力をされている本委員会のみなさまに敬意を表します。
【これまで】
最初に、私のこれまでについて簡単に記させていただきます。父親の影響で5歳から柔道を始めた後、それからは、とにかく競技力向上の活動をメインに突っ走りました。その中で様々な経験をしましたが、29歳の時に(この企画にも登場された、当時、筑波大学教授の)中村良三先生から仙台大学のお話を頂戴し、今日まで22年が経ちます。指導現場では、部長(兼男子監督)と女子監督である妻の南條(旧姓:永井)和恵の指導をサポートしている立場にあります。
在籍22年の間、(この場では語り尽くせない)何かのご縁で、2009年から2016年まで、全日本女子チームのお手伝いをさせていただきました。それ以前の2005年から2008年までは、故斎藤仁先生(当時、男子監督)の全日本男子チームに関わらせていただいたため、約13年間、全日本のお手伝いに関わったことになります。様々なエピソードを所持しておりますが、前述の通り、ここでは語り尽くせませんので、またの機会(?)ということでご了承ください。
【女子柔道との関わり】
次に、私と女子柔道の関りにつきまして。
まず思い出されることは、現在、全柔連女子振興委員をされている山口奈美さん(高校のひとつ上の先輩)のことです。先輩とは小学校の頃、一度だけ試合をしたことがありますが、敗戦を喫しております。高校(新田高等学校)では先輩となるわけですが、当時の監督である浅見三喜夫先生は、「女子を特別だと思ったら、男子は誰ひとり女子と練習しなくなる」の方針のもと、先生ご自身が率先して山口先輩を男子同様(以上)に鍛えられていた様子を思い出します。先輩にとっては、さぞつらい毎日を過ごされていたのではないかと思います(笑)。
次に大学時代ですが、私が進学した筑波大学の女子柔道部員は、日々激しい稽古をしていたという印象が残っております。当時の筑波大学女子は、男子と同じ時間帯で稽古をしていましたが、部員のそのほとんどが日本トップクラスの選手であり(全日本選抜大会を6階級制していた時代)、男子とも乱取をする機会が多くあったように思います。また、監督であった中村良三先生が、試合の一場面(特に寝技)を想定した細かなメニューを設定され、“ピーン”と張りつめた空気の中、男子が稽古を終えてからも延々と練習をしていたことが思い出されます。そのような中で私は、稽古時間中、「女子と乱取をすると、自分の時間が削られてしまう」の発想が先立ち、なるべく女子選手とは目を合わさないようにしておりました。一流選手であれば、そういう機会も自分の糧にするのでしょうが、当時の私にはそのような余裕はありませんでした。
そして41歳の時、様々なタイミングが重なり、全日本女子監督の任を拝命しました。とにかく一流選手たちが相手でしたので、女子選手とどうやって付き合うか、ということよりも「柔道には女子も男子も関係ない」と心の中で考え、勝ちたい執念を燃やす国内トップの選手たちと、どうすれば世界で勝てるかを考え過ごした(今では)懐かしい4年間です。
現在は前述の通り、南條和恵とともに仙台大学柔道部の女子も指導をさせていただいております。彼女が稽古以外でもしっかり学生と向き合い、鍛えてくれているので、手前味噌ではありますが、礼節重視で真っすぐな集団をマネジメントしてくれていると思います。
私たちが子供ころ、「えっ、女子が柔道をやってる!」と驚いた時代から40年が過ぎようとしています。人口減少が加速する中、女子柔道の活動においては全柔連がリードする様々な試みの中、当初と比較しても活性化が進行していると感じます。私としても今後、(男女関係なく)、強さだけではない、真の日本人らしい美しさを表現できる柔道家を育成できる指導者になっていきたいと考えております。
【フランス人から学んだ2つの融合】
最後に、私が全日本女子監督の任を受けていた際に得た経験をひとつだけ記させていただき、現在の指導現場における課題として、みなさまと共有させていただければと存じます。
現在の柔道は、他のスポーツと同様に競技力向上の活動(スポーツとしての柔道)が優先される中で、本来の理念である文化(教育)としての柔道が切り離された考え方で捉われがちです。いわゆる「ダブルスタンダードの解釈」が存在しているということです。そのような流れの中で、この2つの融合の可能性について提言をさせていただきたいと思います。
それは、2014年にフランスナショナルチームとの強化合宿に参加させていただいた時でした。
当時のフランスは、乱取の際に参加者が時間を共有できる「デジタイマー」を利用せず、乱取の区切りはコーチが腕時計でコントロールしていました。乱取終了の時、コーチの「マテ」の号令の後に「レイ」の指示がある形です。「マテ」の後には選手全体が礼をする準備ができるまで「レイ」の発声はされません。20組くらいの乱取りが終了した後、最後の選手が準備できるまで待っていました。中には、思うようにいかず不貞腐れている選手もいましたが、その選手に対しても厳しい声掛けで直させていたことを思い出します。
そのことは、乱取が終わって、最後の礼を正確に行わせるためであることは言うまでもありません。
その時に気づかされました。これまで(現在も)、日本の多くの稽古場において、一本の乱取が終わり、2、30秒程度のインターバルの中で、はだけた上衣を正すことなく略式的な中途半端な礼をする。その後、早く相手を交代する、素早く水分を補給するということがその場の正義となり、正しい「礼」ができなくなっている状況であることを。
競技力向上の活動の中、効率の良い時間の使い方を求めることが常態化され、基本動作を置き去りにしていたのです。正しく私にとって目が覚める出来事でした。
それから所属での乱取においては、間隔を約1分以上取るようにし、必ず乱れた服装を直させ、正しい礼をするように指導しました。現在では習慣化された(させることができた)と思います。
現在、国内外の大会において、試合者に対して正確な礼が求められています。本来であれば、審判員が注意することではなく、プレーヤーが自主的に実践することが望ましいと思います。それは指導者が普段から選手に対してその重要性と必要性を説き、習慣化するよう「時間を作ってあげる」ことが改善のひとつの道ではないかと考えます。
礼は柔道の基本動作の第1項目に提示されています。
少年柔道では正しい礼が徹底されていながら、競技者として成熟する過程において、そのことが疎かになっている現状は否めないと思います。礼という基本動作を、普段の「競技力向上の活動」から正しい形で実践できるよう教育することが、文化の継承と一体化(ダブルスタンダードの融合)させる第一歩になるのではないかと考えます。
色々と綴らせていただきましたが、今回、このような機会をいただいた女子柔道振興委員会に感謝を申し上げ、更には本委員会の益々のご発展を祈念して、終わりとさせていただきます。
(女子柔道振興委員会の推薦により、南條充寿さんに執筆をいただきました。)